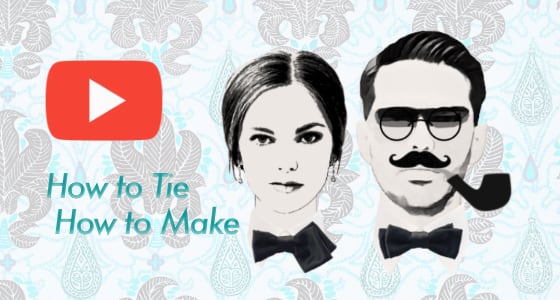2021/08/31 10:43

蝶ネクタイには「手結び型」と「作り結び型」があります。ここでは「手結び型」の結び方について解説いたします。
当ブランドの蝶ネクタイの結び方は、細かく分類すると20種類以上あります。「歴史的に存在した結び方」や「ネクタイやアスコットタイなどの他のネックウェアと同じ結び方」、「新たにブランド独自に考案した結び方」などがあります。
各デザイン形状の特徴や、使用している生地素材によって不向きな結び方もありますので、「全ての手結び型」が「全ての結び方」に対応できるわけではございません。

蝶ネクタイの結び方 23通りリスト
1.蝶結び (Basic bow knot)
2.平行結び (Parallel bow knot)
3.交差結び (Crossed bow knot)
4.片わな結び (One-sided-ring knot)
5.片なが結び (One-sided-long bow knot)
6.リボン結び (Ribbon bow knot) 旧(垂らし結び/Drop bow knot)
7.小型結び (Small bow knot)
8.くわ形結び (Kuwagata bow knot)
9.いちご結び (Strawberry knot)★
10.尾垂れ結び (Tail knot)
11.蝶下げ結び (Mix knot)
12.叶結び (Buckaroo knot)
13.下げ結び (Plain knot)
14.合掌結び (Regate knot)
15.又の字結び (Gordian knot) ★
16.止め結び (Overhand knot) ★
17.覆い結び (Covered knot) ★
18.本結び (Square knot)
19.四つ葉結び (Four-leaf bow knot) ★
20.平行・交差結び (Parallel-cross bow knot)
21.ねじり結び (Twist bow knot)
22.手なが結び (Long-hands bow knot)
23.山結び (Mountain knot)
★マークは留め具が必要

1.「蝶結び」は蝶ネクタイの最も基本的な結び方です。手結びの魅力の1つは、中心部分を絞る時に「縦に入れるプリーツ」や、「両側にできるシワ(ディンプル)」の美しさが演出できる点とも言えます。美意識に正解はないからこそ、自らの感性で楽しむことができます。

2.「平行結び」は19世紀後半頃によく見られる結び方です。結び目の中心にシワが入らないように、上下の水平ラインをほぼ平行にする結び方です。「蝶結び」と同じ手順ですが、絞るのではくピタリと巻き付け、中心を後ろから押し出すように結ぶのがコツです。日本でいう袴の一文字結びと結び目が似ています。

3.「交差結び」は「蝶結び」と同じ手順ですが、角度を斜めにずらす結び方です。19世紀後半から20世紀初頭にかけての蝶ネクタイで、最も多く見られる結び方の1つです。角度に決まりはありませんが、「蝶結び」とは明らかに違った印象を与えます。

4.「片わな結び」は、2つの剣先を同じ方向へ結ぶことが特徴です。ブランドで紹介しているは、蝶ネクタイで美しく結ぶために辿り着いた、独自の手順です。歴史的に、ハンガリーの「マールトン・レンドヴァイ・ジュニア(1830–1875)」という人物の、1860年代のクラバットの結び方などにも確認することができます。

5.「片なが結び」は「交差結び」と同じ手順ですが、片側だけを極端に長くして交差に結びます。左右非対称で印象的なシルエットになります。イタリア人画家「ベルナルド・チェレンターノ(1835-1863)」の肖像画や、ハンガリーの作曲家「フランツ・リスト(1811-1886)」の肖像写真をモチーフに、独自に提案している結び方です。

6.「リボン結び」は剣先を下に垂らす蝶結びです。柔らかい生地で、剣先が自然と垂れるものは除き、張りのある生地でも形を作るための手順を提案しています。歴史的には紅茶ブランド創業者「トーマス・リプトン(1848-1931)」が、この形を愛用していました。

7.「小型結び」は通常の蝶結びより、水平幅を小さく結ぶ方法です。標準的な蝶ネクタイは約12cm幅ですが、「小型結び」は約9cmが目安です。ブランドで独自に提案している手順の他にも、ベルト部分をかなり短く調節して、単に「蝶結び」するという選択肢もあります。歴史的に英国の元首相「ウィンストン・チャーチル(1874-1965)」のトレードマークでもありました。

8.「くわ形結び」はその名の通り、武士の兜[かぶと]のひさしに付いている、くわ形に似ていることから独自に名付けました。「交差結び」と同じ手順ですが、輪になる部分を長く引き出すことで、印象的なシルエットになります。アメリカの歴史家「ウィリアム・プレスコット(1796–1859)」という人物の、1850年代のストックタイが、まさにこの形を表現しています。

9.「いちご結び」はその名の通り、いちごの形に似ていることから、独自に名付けました。手順は寸法を最大限に長くとった状態で「蝶結び」した後、残りの剣先を交差して、ネクタイクリップ等で固定します。歴史的に米国の軍人「アルフレッド・アイバーソン・ジュニア(1829–1911)」という人物の、1860年代のクラバットの結び方に確認することができます。

10.「尾垂れ結び」は片側の剣先を、尾っぽのように垂らす結び方です。独自に辿り着いた手順を提案しています。歴史的に弁護士で軍人の、アルフレッド・ステッドマン・ハートウェル(1836-1912)という人物の、1850年代の肖像写真などで確認することができます。

11.「蝶下げ結び」は「蝶結び」と「下げ結び(Plain knot)」をミックスした形の結び方です。結ぶ手順は独自に辿り着いた方法になり、「尾垂れ結び」と同じですが、垂らす分量や方向を変えることで、異なる形になります。歴史的に、イギリスの小説家「トーマス・ハーディ(1840-1928)」という人物が、ネクタイを使って小さく「蝶結び」した後に、結び下げている肖像写真を確認することができます。

12.「叶結び」は結び目に4つの四角を形作る結び方です。歴史的に北米のカウボーイ・スカーフの結び方の1つとして、「Wild rag knot」や「Buckaroo knot」などと呼ばれています。また米国で1864年に発行された、「ゴディの婦人書」という婦人向け雑誌の中で、女性向けネクタイとしてイラストが紹介されています。日本では、着物の羽織ひもの結び方などとして知られています。第一ボタンを外して首周りを緩めることで、カジュアルなスタイルにもマッチします。

13.「下げ結び」は「(結び下げ)ネクタイ」の最も基本的な結び方ということから、独自に名付けた和名になります。英語ではプレインノット(Plain knot)や、フォアインハンドノット(Four-in-hand knot)とも呼ばれる結び方です。歴史的に20世紀前半頃までは、今のように垂直寸法が均一化しておらず、短いネクタイも存在していました。

14.「合掌結び」は「下げ結び」した後に、敢えて剣先を左右に広げる結び方の和名です。歴史的に1900年代初頭のフランスの商業広告などに、この形状に予め縫い付けられた「作り結びネクタイ」が、「[仏]Régate(リガート)/[英]Regatta(リゲート,レガッタ)」という名称で、しばしば確認できます。添付写真は当時の実物コレクションになります。

15.「又の字結び」は「本結び(Square knot)」した後に剣先を交差し、金具などで留め付ける結び方です。歴史的に1818年に出版された「ネッククロスの世界]という、クラバットの結び方指南書の中でも、「ゴーディアン・ノット(Gordian Knot)」の名で紹介されています。この結び方が最適化され、その後に「プラストロン(アスコットタイの旧称)」となったと考えられます。明治期の日本では、その見た目から「又の字」や「蝉型」と呼ばれました。

16.「止め結び」は一重結び(ひとえむすび)とも呼ばれ、英語では「オーバーハンド・ノット(Overhand knot)」です。ストールやマフラーなど、あらゆるネックウェアで使われてきた、最もシンプルで多く使われている結び方です。金具等で留め付けると収まり良くなります。歴史的に17世紀中頃からヨーロッパで普及した「レース・クラバット(初期のクラバット)」でも典型的な結び方でした。

17.「覆(おお)い結び」は結び目を覆い隠すことから名付けました。見た目は「止め結び」とほぼ同じですが、結び目を作った後に覆うので、より立体感が出ます。金具で留め付けると収まり良くなります。アスコットタイの結び方の1つとして知られています。また、欧米では海運王「アリストテレス・オナシス(1906-1975)」にちなんで、最後に結び目を覆うネクタイ結びを、全て「オナシス・ノット」と呼ぶ傾向にありますが、実際に彼がこの結び方をしていたという証拠写真は見つかっていません。

18.「本結び」は「止め結び」を左右から一回ずつ行い、四角い結び目をつくる方法で、英語では「スクエア・ノット(Square Knot)」と呼びます。歴史的に17世紀中頃から「レース・クラバット(初期のクラバット)」の結び方として確認できます。また19世紀頃から欧米の海軍服の、スカーフの結び方に採用され、「セーラーズ・ノット(Sailor’s Knot)」とも呼ばれます。ある程度の生地の重みと柔さが、剣先を下に垂らすために必要となります。

19.「四つ葉結び」は「四つ葉のクローバー」からインスピレーションを得て、独自に考案した結び方です。手順は「蝶結び」をした後に、4点を同時に回転させて増し締めします。金具で留めて固定する必要があります。

20.「平行・交差結び」は「平行結び」と「交差結び」を掛け合わせた結び方です。結び目を絞らないので、「交差結び」とはまた違う印象になります。歴史的に19世紀後半の肖像写真でしばしば確認でき、初期の「手結び蝶ネクタイ」らしい結び方の1つです。。

21.「ねじり結び」は独自に考案した結び方です。手順は「蝶結び」した後に意図的にねじることで、ユニークな立体感を出すことができます。明確なシルエットを出すためには、剣先の幅が6cm以上あることが望ましいです。

22.「手なが結び」は「蝶結び」の端を、あえて長く伸ばす結び方です。歴史的に19世紀後半の肖像写真でしばしば確認できます。イギリスのイラストレーターだった、オーブリー・ビアズリー(1872-1898) という人物も好んで結んでいたようです。

23.「山結び」はその名の通り、山の形をつくる結び方です。作曲家「リヒャルト・ワーグナー(1813-1883)」の結び目をモチーフに、独自に導き出しました手順です。剣先は両下の斜め45度方向に向くので、水平方向に結ぶ「蝶結び」とはまた違う印象になります。
結び方の手順は動画でもシェアしております。
「蝶ネクタイの結び方 簡単講座 結ぶ人アングル」
蝶ネクタイ 手結び型 商品ページはこちら